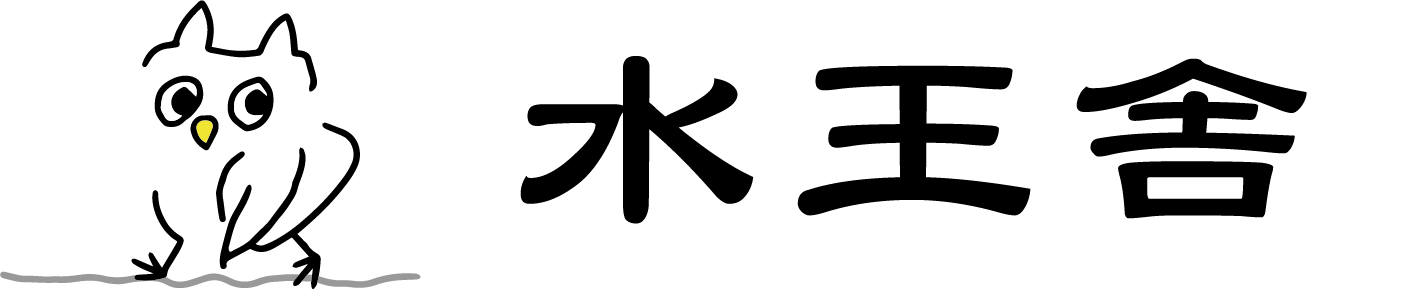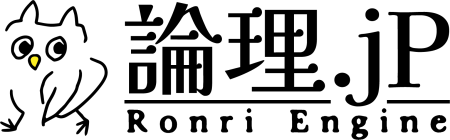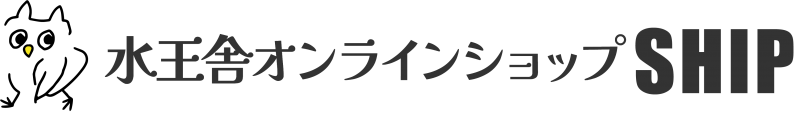出口汪のルーツとは
実は、幼い頃から、昼行灯(ひるあんどん)然としていた。いまでもそれは変わらない。目的地を確認することなく歩き出した後で迷う。蛍光灯の替え方がわからず考えあぐね、しまいには「この電灯は、一度切れたら買い直さなくてはいけない代物だ」と結論づける。「計画性はないし、どこが論理的なんだと思うことばかりで呆れますよ」と妻の寿美子は笑う。「ダイエットしなきゃとよく言うんですが、普通は“明日から始める”と言うでしょう?それが“明後日から”って宣言して、絶対に実行しない」
曽祖父は「大本」の教祖
 曽祖父は「大本」の教祖、出口王仁三郎。「三千世界一度に開く梅の花艮の金神の世に成りたぞよ。(略)三千世界の立替え立直しを致すぞよ」。目に一丁字もない開祖、出口なおが神懸かりで書いたこのお筆先で知られる大本は、「立替え立直し」という革命思想ゆえに天皇制と鋭く対峙し、戦前、治安維持法、不敬罪により苛烈な弾圧を受けた。特に王仁三郎の現人神の戯画化にも見えるトリックスターぶりは当局の敵愾心を煽った。
曽祖父は「大本」の教祖、出口王仁三郎。「三千世界一度に開く梅の花艮の金神の世に成りたぞよ。(略)三千世界の立替え立直しを致すぞよ」。目に一丁字もない開祖、出口なおが神懸かりで書いたこのお筆先で知られる大本は、「立替え立直し」という革命思想ゆえに天皇制と鋭く対峙し、戦前、治安維持法、不敬罪により苛烈な弾圧を受けた。特に王仁三郎の現人神の戯画化にも見えるトリックスターぶりは当局の敵愾心を煽った。
ともあれ昭和初期に800万人の信徒を従え、民衆から知識人や高級官僚、軍人まで絶大な影響を与えたのは間違いない。そうした怪人の影響はしかし、出口の幼少期に直接は見当たらない。むしろ「信者さんが年端もいかない子どもの自分を“汪様”なんて呼ぶから、宗教的な雰囲気がどうも苦手なようでした」と避けるふうだったと言う。
「苦手なようでした」と他人事のように出口が語るのは、幼少期の記憶があまり定かではないからだ。「いつ何をしていたか、両親は何を生業にしていたのか。いまでもよくわかっていない」
ヤクザを更生させるほど常識はずれで鷹揚な両親
 父、和明も大本と距離を置き、早稲田大学を中退後、貸本屋、喫茶店の経営、女子大の講師と職業や住居を転々としていたせいもある。だが、より根本的には、細事にこだわる必要も感じないほど、和明も母、礼子も出口の茫洋さの上を行く鷹揚な人物だったからだろう。
父、和明も大本と距離を置き、早稲田大学を中退後、貸本屋、喫茶店の経営、女子大の講師と職業や住居を転々としていたせいもある。だが、より根本的には、細事にこだわる必要も感じないほど、和明も母、礼子も出口の茫洋さの上を行く鷹揚な人物だったからだろう。
両親が1週間だけコーヒーの入れ方を学び、見よう見まねで東京・目黒に喫茶店を開店したときだ。間もなく地元のヤクザが「うちの面倒みてくれよ」と暗にみかじめ料を要求してきた。礼子はこう回想する。「てっきりこの方は喫茶店の経営を学びたくて、その面倒をみて欲しいと言ってるんだと思いました。私たちはおコーヒーの入れ方を大まじめに教えたんです。そうしたら違うんですね」
両親は世間の常識と懸隔していた。だが暗愚だったわけではないのは、和明の影響でヤクザは足を洗ってしまったことからも窺えるだろう。人を自然と暗がりから引き上げる底なしの明るさがあった。
どこか「ずれていた」少年時代
そうした打算抜きの生き方は後先考えないことにもつながり、出口は日々のたつきに追われる両親と一緒に遊んだり、話したこともほとんどないという。
いつも眠くて仕方がない
 では、出口少年は寂しい毎日を送っていたかと思いきや、弟の面倒を甲斐甲斐しく見つつも、「妄想に耽っていました。いまの自分ではない自分を思い浮かべてボーッとしていました。とにかくいつも眠くて仕方なくて、学校では突っ伏して寝てました」と、自分を取り巻く現状にさほど関心がなかった。
では、出口少年は寂しい毎日を送っていたかと思いきや、弟の面倒を甲斐甲斐しく見つつも、「妄想に耽っていました。いまの自分ではない自分を思い浮かべてボーッとしていました。とにかくいつも眠くて仕方なくて、学校では突っ伏して寝てました」と、自分を取り巻く現状にさほど関心がなかった。
「ボーッとしていた」と連呼する出口だが、幼い頃、よく遊んだという従兄弟の出口光は、異なる印象を抱いていた。
「大人を相手に堂々と話をしていたし、とにかく弁が立った。今になって初めてボーッとしていたと聞いたけど、てっきりしっかり者だと思っていた」
「弁が立つ」「しっかりしている」という印象を少年期の出口に感じていたものは多い。だが出口はこう言う。
「人にはしっかりしているとよく言われますが、そもそも考えてしゃべっていないし、何を話したのか覚えていない」
左右違う靴を履くほど無頓着
 加えて、人からどう見られるかにも関心がないから、服装にも無頓着で、左右違う靴を平気で履きもした。
加えて、人からどう見られるかにも関心がないから、服装にも無頓着で、左右違う靴を平気で履きもした。
「人は何に価値を置いているか、人の心が本当にわからなかった。かといって、そのことに悩むわけでもなく、きちんとものを考えたこともなく、なんだかモヤモヤしたものがいつも周りにあった感じがします」
ひとりの時はボーッとしているが、他人と接する時は、考えるまでもなくひとりでに言葉が口をついて出た。いや、出口なりに考えてはいた。
たとえば持ち物をすぐ失ってしまう出口は、冬に手袋をなくすと手がかじかむことに困り、よくよく考えた末、「足は靴に保護されているから外気にあたっていない。靴下を脱いで手袋にしたらいいんじゃないか」と靴下を手にはめて登校していた。まわりは唖然としたらしい。
言葉を持った瞬間、世界は天と地にわかれた
 出口の記憶が多少鮮やかになり始めたのは中学2年のとき、家が京都・亀岡に腰を落ち着けてからだ。父、和明はいつの間にか小説家になっていた。無名の新人でありながら毎日新聞社で、出口王仁三郎をはじめ教団の歴史を描いた『大地の母』の書き下ろしによる刊行を開始する。登場人物の戸籍すべてを調べるといった徹底した取材を行っている父の様子を垣間見るうち、小説家に憧れ、漱石や鴎外を好んで読むようになる、自分でも小説を書いてみたが、「ひとりよがりな考えを書いたにすぎない」もので、プロットも明確ではなかった。大学受験を前に作家志望はしばらく潜行することになる。
出口の記憶が多少鮮やかになり始めたのは中学2年のとき、家が京都・亀岡に腰を落ち着けてからだ。父、和明はいつの間にか小説家になっていた。無名の新人でありながら毎日新聞社で、出口王仁三郎をはじめ教団の歴史を描いた『大地の母』の書き下ろしによる刊行を開始する。登場人物の戸籍すべてを調べるといった徹底した取材を行っている父の様子を垣間見るうち、小説家に憧れ、漱石や鴎外を好んで読むようになる、自分でも小説を書いてみたが、「ひとりよがりな考えを書いたにすぎない」もので、プロットも明確ではなかった。大学受験を前に作家志望はしばらく潜行することになる。
出口が幼い頃からずっと感じていた「周りにあったモヤモヤ」が晴れ始めたのは、院生時代に始めた大阪での予備校講師のアルバイトがきっかけだった。いきなり60人の生徒を相手にしなければならなかったものの「ひたすらテキストを読んで感じたことをしゃべっていた」と、いつもの彼のままで滑らかに話はできた。これまでは自分のそうした勝手に口から零れる言葉を振り返る必要はなかった。だが、「落ちこぼれの子が多く、どうにかして生徒の実力を伸ばしたい。どう教えたらいいか根本的に考え始めました。」
要は「よく考えてから話す必要にかられた」という至極当たり前の行為が、出口を目覚めさせた。多くの人にとって、自分がこれから話す言葉について考えることは、当然に過ぎることだろう。しかし、それまでの彼にとって言葉は肉体にこもったものでしかなかった。言葉は操れるもの、つまり他者だという発見は新しい経験だった。
そこで出口が知ったのは、「熱いという感覚も“熱い”という、言葉がなければ認識されない。言葉が世界を生んでいる」という言語観だった。その考えに至ったときの驚きをこう表す。「言葉がないとき空は空でなく混沌だった。言葉を持った瞬間、世界は天と地にわかれた」
言葉が不分明な混沌を切り取り、世界を成り立たせている。発した言葉が秩序をもたらすことを理解したとき、「周囲のモヤモヤ」した光景は晴れた。
 曽祖父は「大本」の教祖、出口王仁三郎。「三千世界一度に開く梅の花艮の金神の世に成りたぞよ。(略)三千世界の立替え立直しを致すぞよ」。目に一丁字もない開祖、出口なおが神懸かりで書いたこのお筆先で知られる大本は、「立替え立直し」という革命思想ゆえに天皇制と鋭く対峙し、戦前、治安維持法、不敬罪により苛烈な弾圧を受けた。特に王仁三郎の現人神の戯画化にも見えるトリックスターぶりは当局の敵愾心を煽った。
曽祖父は「大本」の教祖、出口王仁三郎。「三千世界一度に開く梅の花艮の金神の世に成りたぞよ。(略)三千世界の立替え立直しを致すぞよ」。目に一丁字もない開祖、出口なおが神懸かりで書いたこのお筆先で知られる大本は、「立替え立直し」という革命思想ゆえに天皇制と鋭く対峙し、戦前、治安維持法、不敬罪により苛烈な弾圧を受けた。特に王仁三郎の現人神の戯画化にも見えるトリックスターぶりは当局の敵愾心を煽った。